感染性腸炎
感染性腸炎
お子様の急な嘔吐や下痢で心配されている保護者の方へ。
感染性腸炎は小児に頻発する疾患であり、適切な対処と治療が重要です。当院では、感染性腸炎の診断から治療まで、小児科専門医による医療を提供しています。

感染性腸炎とは
「うちの子が急に嘔吐を繰り返して、熱も出てきました。これって感染性腸炎でしょうか?」このような不安を抱える保護者の方は少なくありません。
感染性腸炎は、ウイルスや細菌などの病原体が消化器系に感染することで引き起こされる疾患です。
感染性腸炎は小児科外来で最も多く診られる疾患の一つであり、年間を通して発症が見られます。
感染性腸炎の特徴として、主に嘔吐、下痢、発熱といった消化器症状が現れることが挙げられます。
これらの症状は、病原体の種類や患者の年齢、免疫状態によって重症度や経過が大きく異なります。感染性腸炎は、ウイルス性腸炎と細菌性腸炎に大別され、それぞれ異なる治療アプローチが必要となります。
感染性腸炎の原因
感染性腸炎の原因となる病原体は多岐にわたり、ウイルスでは主にノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスが、細菌では主にカンピロバクター、サルモネラ菌、病原性大腸菌などが挙げられます。
小児の感染性腸炎の約70-80%はウイルス性であり、特に冬季に多く見られます。
病原体の種類により感染経路が異なり、ウイルス性では飛沫感染や接触感染、細菌性では主に経口感染(汚染された食品や水の摂取)が主要な経路となります。
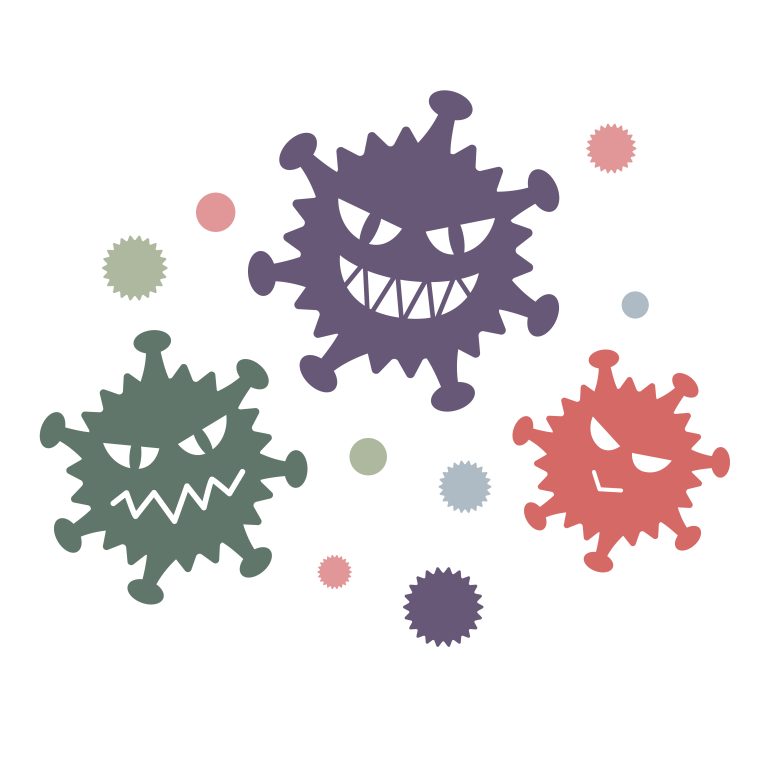
◆ウイルス性感染性腸炎の原因
ノロウイルスは感染性腸炎の代表的な原因ウイルスで、特に11月から3月の冬季に流行のピークを迎えます。
ロタウイルスは主に乳幼児に重篤な症状を引き起こし、脱水症状による入院が必要となることが多い感染性腸炎の原因です。アデノウイルスは年間を通して見られ、比較的軽症の感染性腸炎を引き起こします。
◆細菌性感染性腸炎の原因
細菌性の感染性腸炎は主に夏季に多く発症し、食中毒の形で集団発生することがあります。
カンピロバクターは鶏肉を介した感染が多く、サルモネラ菌は卵や鶏肉、ペットからの感染が報告されています。
病原性大腸菌O157などの腸管出血性大腸菌による感染性腸炎は、重篤な合併症を引き起こす可能性があるため特に注意が必要です。
感染性腸炎の症状
急性発症の嘔吐、下痢、腹痛、発熱が主要な症状で、脱水症状を併発する場合があります。

◆ウイルス性感染性腸炎の症状
ウイルス性の感染性腸炎では、多くの場合、嘔吐症状が最初に現れます。
特にノロウイルスによる感染性腸炎では、突然の激しい嘔吐で発症することが特徴的です。
嘔吐は通常1-2日間続き、その後水様性の下痢が始まります。発熱は38℃前後の微熱から中等度の発熱が見られますが、高熱となることは比較的少ないです。
ロタウイルスによる感染性腸炎は、特に乳幼児で重篤な症状を呈することがあります。大量の水様便により急速な脱水症状が進行し、電解質異常を併発することがあります。
◆細菌性感染性腸炎の症状
細菌性の感染性腸炎では、下痢が主要な症状として現れることが多く、しばしば血液や膿が混じることがあります。
特に腸管出血性大腸菌による感染性腸炎では、激しい腹痛と血便が特徴的で、溶血性尿毒症症候群(HUS)などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。
カンピロバクターによる感染性腸炎では、発症前2-5日間の潜伏期間の後、発熱、腹痛、下痢の三徴が現れます。
サルモネラ菌による感染性腸炎では、高熱(39℃以上)を伴うことが多く、時として菌血症を併発することがあります。
◆感染性腸炎を放置した場合のリスク
適切な治療を受けずに放置すると、重篤な脱水症状、電解質異常、さらには意識障害や腎機能障害などの合併症を引き起こす可能性があります。
◆感染性腸炎の治療後の経過や注意点
多くの場合、適切な治療により1週間程度で症状は改善しますが、完全な回復まで2-3週間を要することもあります。
治療後も腸内環境の正常化まで時間がかかるため、食事内容の調整や感染予防策の継続が重要です。特に家族内感染を防ぐため、手洗いの徹底や消毒が重要です。
家庭で気を付けること
感染性腸炎の家庭での管理は、患者の回復促進と家族内感染の予防という二つの重要な側面があります。
家庭での適切な対応により感染性腸炎の重症化を予防し、早期回復を図ることができます。
◆水分・電解質管理
感染性腸炎における最も重要な家庭での管理は、適切な水分・電解質補給です。
嘔吐や下痢により失われる水分と電解質を適切に補充することで、脱水症状の進行を防ぐことができます。経口補水液(OS-1、アクアライトなど)を使用し、少量ずつ頻回に摂取させることが効果的です。
脱水症状のサインとして、尿量の減少、口唇の乾燥、皮膚の弾力性低下、活気の低下などがあります。これらの症状が認められた場合は、速やかに医療機関を受診することが必要です。
◆食事管理と回復期の栄養
感染性腸炎の急性期には、消化管の安静を保つため、無理な食事摂取は避けるべきです。
嘔吐が治まり、水分摂取が可能となった段階で、段階的に食事を再開します。
最初は消化の良い炭水化物(おかゆ、うどん、パンなど)から開始し、症状の改善に応じて蛋白質や脂質を含む食品を徐々に追加していきます。
回復期の食事として推奨されるのは、バナナ、米、りんご、トーストなどの「BRAT食」です。
これらの食品は消化が良く、下痢症状の改善に寄与するとされています。一方、乳製品、脂肪分の多い食品、刺激的な香辛料、カフェイン含有飲料などは、症状が完全に改善するまで避けることが推奨されます。
感染予防策
感染性腸炎は高い感染性を持つため、家庭内での二次感染予防が極めて重要です。
患者の便や嘔吐物には大量のウイルスや細菌が含まれているため、適切な処理と消毒(100倍に薄めた塩素系漂白剤)が必要です。
手洗いは最も基本的で効果的な感染予防策です。石鹸と流水で30秒以上の十分な手洗いを、患者のケア後、食事前、トイレ後に必ず実施してください。

当院では、感染性腸炎の診断から治療、回復期の管理まで、包括的な医療を提供しています。豊富な診療経験に基づき、患者一人ひとりの症状や重症度に応じた治療計画を立案します。
